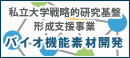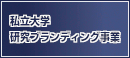【KAIT産学官連携メルマガ】情報学部 情報システム学科特集(2025年6月13日号)
【KAIT産学官連携メルマガ】情報学部 情報システム学科特集(2025年6月13日号)
※本メールマガジンは、神奈川工科大学(KAIT)が主催するシンポジウム等に参加された方、展示会等で名刺交換させていただいた方、関係機関の方々に配信しております。
※配信先の変更・停止をご希望の方は、末尾をご参照ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
目次
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】新着ニュース
【2】YouTube「神奈川工科大学 研究推進機構チャンネル」
【3】研究・技術シーズ紹介(情報学部 情報システム学科)
●全ての人のQOL向上を目指したライフサポートシステムの開発
●オートエンコーダを用いたロボットアームの異常検知
●健康寿命を延伸する共生型ロボットAIの研究開発
●視覚障害者立体聴覚ARナビゲーションインタフェースの開発
●地域・組織間連携による高齢者の健康を支援
●高齢者向けインテリジェント・パーソナル・モビリティー・ビークルの開発
●健康管理および見守り用ロボット・システムの開発
●無伴奏歌唱(ア・カペラ)に合わせて手拍子を打つロボット
●お部屋整理整頓ロボットの開発
●流体アクチュエータを用いたロボット・防災災害救助用ロボットの開発
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】新着ニュース
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
情報学部情報工学科 画像情報処理システム研究室が開発した「読話クラブ」アプリが紹介されました
https://cp.kanagawa-it.ac.jp/news/3098.html
Interop Tokyo 2025に向けて超広帯域ネットワーク研究センターがキックオフミーティングを行いました
https://www.kait.jp/tech_news/tech_20250530.html
2025.8.8㈮ 【夏休み子ども向けイベント】KAITサイエンスサマーを開催します
7月1日10時より参加申し込み開始予定(先着順)となります。ぜひ遊びに来てください。
https://cp.kanagawa-it.ac.jp/uncategorized/3006.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】研究・技術シーズ紹介
《特集》情報学部 情報システム学科
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●全ての人のQOL向上を目指したライフサポートシステムの開発
ライフサポートシステム研究室 教授 入江慎治
地域には、健康な人、病気や障害を持った人など様々な人が暮らしています。医療や介護が必要な人が、必要な医療や介護が受けられるためには、地域包括ケアシステムの充実などのライフサポートシステムの整備が必要です。
また、医療や介護が必要とならないよう、健康もしくは未病の段階から必要な予防行動をとることも重要であり、そのためにも地域の人々の健康関連データに基づいた予防も含めたライフサポートシステムを構築する必要があります。ライフサポートシステムを開発することで、地域住民のQOL向上を目指しています。
【研究室紹介はこちら https://www.kait.jp/research/navi/irie.html】
●オートエンコーダを用いたロボットアームの異常検知
知能インタフェース研究室 教授 河原崎徳之
今日、多くのロボットアームが様々な場所で稼働していますが、電源電圧の低下やセンサ信号の誤差、摩擦による影響など、様々な原因で正しく動作しないことがあります。また、ロボットによる作業のさらなる自動化を進めるにあたり、ロボット動作の異常検知も人の手で行わないことが望ましいです。 本研究では、ロボットアームのモータ電流の変化に着目し、この電流変化から動作の異常を検知するシステムを開発しました。具体的には、教師なし機械学習の一つであるオートエンコーダを使用して、ロボットアームの異常を自動で検知することを目標としています。
【研究室紹介 https://www.kait.jp/research/navi/kawarazaki.html】
●健康寿命を延伸する共生型ロボットAIの研究開発
人間機械共生研究室 准教授 三枝 亮
これまで人間の道具に過ぎなかった計算機やロボットは、不完全ながらも知能や感性のかけらをもつようになり、人間にとってのある種のパートナーとなりつつあります。しかしながら、人間は「人工物を完全に支配できなければ危ない」という恐れの念からなかなか脱却できず、人工物からの問いかけを見出すことや一緒に試行錯誤すること、また、それらに起因した成長発達の機会を逃しています。そこで、ロボット三原則を打破するような、人と人工物の新しいエコシステムを創ることが、当研究室のミッションです。人の能力を補い、未知なる能力を引き出すパートナーと暮らすことが、人の健康寿命を延伸させるきっかけにもなるだろうと考えています。
【研究室紹介 https://www.syblab.org】
研究開発の近況を少し紹介させていただきます.
・介護の見聞録(2024年7月・名古屋テレビ・https://www.kait.jp/news/post_157.html)
・国際共同ワークショップ(2024年12月・バンコク)
・神奈川県共生社会実践セミナー(2024年12月・神奈川県本庁舎・
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m8u/kyousei-forum.html)
・学生奨励賞 (2025年3月・情報処理学会・https://www.kait.jp/news/post_278.html)
・階段昇降車いす共同研究開始(2025年4月・相模原)
●視覚障害者立体聴覚ARナビゲーションインタフェースの開発
人間工学研究室 教授 高尾秀伸
立体音響技術を用いて生成した仮想音像を屋内の実音響空間に重畳することで、立体聴覚AR(拡張現実)インタフェースを開発しています。これを用いて、自分が向かうべき方向を示す仮想音像の空間的な位置をナビゲーション情報として呈示します。これにより、従来の音声誘導方式では極めて困難であった視覚障害者の屋内における単独歩行が可能となりました。
今後実用化に向かうことで、公共施設、ショッピングモール等商業施設、パラスポーツ競技場等における屋内誘導が可能となり、視覚障害者のQOL向上に大きく貢献することが期待されます。
【研究室紹介 https://www.kait.jp/research/navi/takao.html】
●地域・組織間連携による高齢者の健康を支援
運動機能評価研究室 教授 高橋勝美
少子高齢化社会における日本の健康施策は、健康寿命の延伸を目指し、成長戦略としてのヘルスケア産業の振興や健康データの見える化がすすめられています。本研究室では、フレイル予防を目指し、地域連携や組織間連携を構築し、高齢者の運動機能を簡易に測定評価できる機器を産学連携で開発し、その機器を用いたロコモティブシンドロームの見える化をフィールドワークで行っています。
健康寿命の延伸は、下肢機能の低下を予防することであり、高齢者の下肢筋力評価やADLの特性を分析することで、ロコモ予防に必要なエビデンスを収集します。地域と連携して高齢者の健康支援を進めることは、厚生労働省が進めている「地域包括ケアシステム」構築の一助となります。
【研究室紹介 https://www.kait.jp/research/navi/ktakahashi.html】
●高齢者向けインテリジェント・パーソナル・モビリティー・ビークルの開発
人間支援システム研究室 教授 高橋良彦
近い将来訪れる超高齢化社会では、高齢者が自立した生活をすることが重要となります。
自立した生活では、たとえば食糧の買い物等でスーパーに一人で行くこと等が考えられます。その場合、歩道やでこぼこ道を安全に移動しなければなりません。またスーパー等の人混みでも接触せずに移動しなければなりません。また夜に充電を忘れると翌日にすぐに外出でない等の問題もあります。
そのような状況でも、安全に安心して使用できる人間工学とロボティクスを統合した知的移動体「インテリジェント・パーソナル・モビリティー・ビークル」を開発しています。
【研究室紹介 https://www.kait.jp/research/navi/ytakahashi.html】
●健康管理および見守り用ロボット・システムの開発
知能機械研究室 教授 兵頭和人
高齢者にとって継続的に血圧、脈拍数、体温などのバイタルサインを計測することは健康を管理する上で重要であり、適度な運動を行うことは健康を維持する上で重要です。
しかし、自発的に健康状態の把握・運動を継続することは難しいため、バイタルサインの計測や適度な運動を促すための働きかけを行うシステムが必要です。また、核家族化の影響により育児に関する知識が不足する状況が生じ、育児への不安が増加しています。そのため、乳幼児のバイタルサインを計測し医師や保育士のアドバイスを受ける仕組みが必要です。
本研究では日常生活の中で手軽に高齢者や乳幼児の健康状態や日常生活におけるリスクの把握を行い、健康を維持するために楽しく身体を動かせるように働きかける機能を有するロボット・システムの開発を行っています。
【研究室紹介 https://www.kait.jp/research/navi/hyoudou.html】
●無伴奏歌唱(ア・カペラ)に合わせて手拍子を打つロボット
ユニバーサルロボット研究室 准教授 吉留忠史
人が歌うのに合わせて手拍子をしてくれるロボットを開発しています。
歌を歌うことは、ストレス発散、心肺機能の維持・増進、脳の活性化につながり、高齢者の健康維持・増進に寄与します(音楽療法)。歌うことを習慣化することが望ましいですが、ひとりで歌うのも寂しいものです。そんなとき、ロボットが歌を聴いてくれて手拍子もしてくれるならば、歌を歌いたくなると考えています。技術面では、音声の長さや音高から手拍子しやすいテンポを推定することが課題となり、時系列上の音量の立ち上がりや音高の変化を周波数解析することで、基本周波数とその倍数にテンポが現れることを利用します。人が一定のテンポで歌うことは難しく、それをリアルタイムで得ることはさらに難しいですが、人が違和感を感じずに手拍子が始まることを目指して開発しています。
【研究室紹介 https://www.kait.jp/research/navi/yoshitome.html】
●お部屋整理整頓ロボットの開発
ロボット・ビジョン研究室 教授 吉野和芳
iRobot社のルンバに代表されるようなロボット掃除機は部屋を自動で動き回りながらちりやほこりを回収します。しかし、その普及率は10%に満たないのが現状で、その理由の一つに、ロボット掃除機のために、床の上にある比較的大きなものを片付ける手間があります。
そこで本研究では、床上にある子どものおもちゃや雑誌など比較的大きなものを画像処理によって見つけ、それらをロボットアームで回収し、指定された場所に片付ける整理整頓ロボットの開発を行っています。
具体的には、整理整頓ロボットが自動で移動しながら片付ける対象を見つけるための室内環境マップの作成方法、画像処理による対象物の判別方法、対象物の形状認識と把持機構の開発などに関して研究を進めています。また、現在のロボット掃除機は床の上にあるものを避けながら進んでいくため、その付近は掃除されません。そこで、整理整頓ロボットが現在販売されているロボット掃除機と連携して、床の上にあるものを一時的にずらし、そのものの下を掃除させ、また元に戻すという整理整頓ロボットについても検討を進めています。
【研究室紹介 https://www.kait.jp/research/navi/yoshino.html】
●流体アクチュエータを用いたロボット・防災災害救助用ロボットの開発
フルードパワー・災害救助ロボット研究室 教授 吉満俊拓
当研究室では、流体を用いた人に関わる様々な機器・ロボットの開発を行っています。
特に空気圧を用いたアクチュエータは柔軟な動きが得意で軽量です。その特徴を生かし、不整地・傾斜地では活動を妨げない自由な動きと、怪我・捻挫が起きないように関節の動きを補助する、という相反する機能を有するアシストスーツや、空気圧人工筋を用いて指・手首を曲げることで仮想空間における力覚提示を補助するグローブ、自走できる車いす生活者を対象として、屋内生活における段差を解消し、「排泄と入浴」が移乗をせずに可能とするフリーアクセス車いすなど、人にやさしく環境負荷の少ない福祉機器や、防災・災害救助機器の研究を行っています。
【研究室紹介 https://www.kait.jp/research/navi/yoshimitsu.html】