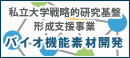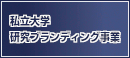【KAIT産学官連携メルマガ】工学部 機械工学科特集(2025年11月7日号)
【KAIT産学官連携メルマガ】工学部 機械工学科特集(2025年11月7日号)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
目次
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】新着ニュース
【2】関連動画
【3】研究・技術シーズ紹介(機械工学科)
●ロボット機構のキネマティクス
●超音波振動援用技術を用いた難削材の高精度研削・切削加工
●電動レーシングカートERK:Electric Racing Kartの開発
●オフセットローラー曲げ加工(低周波振動付与による加工限界の改善)
●車両運動と車体姿勢を独立に再現するドライビングシミュレータの開発
●上部集熱式熱サイホン
●心地よいヒューマン-マシンインターフェイスの開発
●高速道路でのV2V合流支援システムに必要な無線通信の条件抽出
●熱機関の性能向上に関する研究
●ネットワーク情報共有型AIモビリティの研究
●教育に活用する機械の検討
●計測結果に基づいた実用的交通流物理モデルの開発と高速道路交通流での評価
●燃焼の数値シミュレーションによる燃焼排出物の評価
●ターボ圧縮機に発生する非定常流動の予知・制御に関する研究
●超音波による工具接触圧力分布測定法に関する研究
●交通事故削減に資する車両運動制御技術の研究
●デザイン科学と破壊学に関する研究
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】新着ニュース
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
電子ビーム描画装置を用いた光デバイスの研究―アイディアを形にする微細加工技術―(先端工学研究センター・ナノテクノロジー研究室/超高速光機能回路研究室 電気電子情報工学科 教授 中津原 克己)
https://www.kait.jp/tech_news/tech_20251016.html
【開催報告】心療内科医による特別講義&ワークショップ『痛みが視えれば世界は変わる 自分の痛みをハックせよ』
https://www.kait.jp/tech_news/tech_20251023.html
世界の大学を結ぶ大学間メタバース(グローバル学術連携センター/情報工学科 教授 鷹野 孝典)
https://www.kait.jp/tech_news/tech_20251031.html
【情報工学科】 障害者自立支援機器ニーズ・シーズマッチング交流会2025に出展します
https://cp.kanagawa-it.ac.jp/event/3663.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】関連動画
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4月に開催した第3回リサーチデーの研究内容紹介動画です。
【オープンラボ紹介】着氷風洞の活用ー航空機への着氷とその影響についてー
https://youtu.be/sRTAOICpeNU?si=uTZsqLL0kg5MgfmB
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】研究・技術シーズ紹介
《特集》工学部 機械工学科
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●ロボット機構のキネマティクス
ロボット機構学研究室 教授 有川敬輔
本研究室では、キネマティクス理論をベースとして、非定型的な構造を持つ様々なロボット機構の研究開発を行っています。例えば、テンセグリティ構造(棒材とワイヤーで構成される構造)とパラレル機構を組み合わせたロボットアームは、構造自体を折りたたむことが可能となっています。また、複数の動作モードを有する流体駆動のマニピュレータは、バルブ操作によって基本運動学特性を変更することが可能となっています。この他、ロボット機構のキネマティクス理論を応用し、タンパク質をはじめとする生体機能分子の運動解析の研究にも取り組んでいます。
【研究室紹介 https://www.kait.jp/research/navi/arikawa.html】
●超音波振動援用技術を用いた難削材の高精度研削・切削加工
精密加工研究室 教授 今井健一郎
切削や研削において、被削材の強度、硬脆性、耐熱性等は難削性に直結します。しかし、これらの機械的特性は材料としては有用です。本研究では、どうしたら加工を容易に行えるのかを実験的に試みています。例えば、研削ホイールの半径方向に超音波振動を援用する研削法では、ホイール作用面の砥粒を材料に衝撃的に働かせることで砥粒1つ1つの材料除去能力を高められると考えています。しかし、この高周波の方法では材料の除去機構の解明が難しいため、模擬的にダイヤモンドバイトを砥粒に見立てた低周波の振動援用切削加工を行い、除去機構の解明も目指しています。
【研究室紹介 https://www.kait.jp/research/navi/imai.html】
●電動レーシングカートERK:Electric Racing Kartの開発
モータースポーツ工学研究室 准教授 岡崎昭仁
喫緊の課題である地球温暖化対策のために自動車、モビリティの電動化が急進展しています。電動車両はエンジン車両と比較して構成はシンプルに見えますが、電動システムのパッケージ技術、電池の寿命予測など課題は多いです。本研究室では、高速かつ高負荷、加えて軽量でコンパクトさが求められるERKの電動化を行うことで、主に小型モビリティの電動化技術開発を行っています。開発中のERKは、廉価な電動機とインバータを使用し、オリジナルな安全装置を組み込んだジャンクションボックスを搭載し、レースという過酷な環境下で電池の寿命予測技術開発などを推進しています。将来的に小型モビリティ用電動システムとして市場供試を目指して日夜研究開発に取り組んでいます。
【研究室紹介 https://www.kait.jp/research/navi/aokazaki.html】
●オフセットローラー曲げ加工(低周波振動付与による加工限界の改善)
モータースポーツ工学研究室 助教 加藤俊二
電気自動車等のアルミニウムスペースフレームに用いられる形材の曲げ加工は自動車の設計に合わせて、軸方向に曲率を変えて曲げる必要があります。そのための加工法として、スペースフレームをガイドローラーに通し、オフセットされたローラー(曲げローラー)に当て、曲げを行う加工法を提案しており、曲げローラーの位置を変えることにより、曲率を変えることができます。曲げ加工中に被加工材に生じる断面変形および曲げ内側のしわを低周波振動の加工力を付与することにより低減できることを実験的に明らかにし、加工限界の改善がはかれることを示しました。付与する低周波振動の周波数、振幅を変えて断面変形およびしわの抑制効果への影響を検討しています。
【研究室紹介 https://www.kait.jp/research/navi/kikuchi.html】
●車両運動と車体姿勢を独立に再現するドライビングシミュレータの開発
車両運動・制御研究室 助教 狩野芳郎
一般的なドライビングシミュレータは、車両に発生する加速度を6軸リンクによる並進運動と傾斜により模擬するので、実車とは体感が異なります。そこで、本研究では6軸リンクに加えてリニアレールとヨーリングにより前後左右の車両運動と車体姿勢を独立して再現できるドライビングシミュレータを開発しました。これにより、走行中の車両姿勢がドライバーに与える影響について、ドライバパラメータ同定手法と生体反応計測等を用いて明らかにしています。
【研究室紹介 https://www.kait.jp/research/navi/yamakado.html】
●上部集熱式熱サイホン
ソーラービークル研究室 助教 川口隆史
太陽熱を利用する熱サイホンの研究を行っています。外部電源を使わずに熱移動できる熱サイホン、特に屋根の上に設置した太陽熱集熱器から地上に熱エネルギーを移動することを目的にした上部加熱式(トップヒート式)熱サイホンに注目し、構造が比較的簡単な蒸気泡ポンプ方式により実証実験を行ってきました。この方式は1970年代より研究され、プレハブのモデルハウスに設置した熱サイホンにより高低差4mの循環を実現するとともに小規模の発電ができることを実証しました。しかし屋外に設置したモデルハウスによる実証実験では、朝や夕方の太陽熱が少ない状況において、熱の移動、すなわち作動流体の循環が間欠的となる問題が残されています。この間欠的な流動は太陽熱集熱器での突沸等システム故障の原因となります。安定した熱移動を実現するため、エナジーハーベストによる電力を用いた制御システムを開発しています。現在、制御を実現するために管内圧力を下げることを提案し、小規模な実験装置で作動流体の間欠的な循環を安定化できることを確認しました。今後、実機レベルでの運用を目指します。
また、競技用ソーラーカーの機器類の温度や振動を中心とする耐環境性能についても調査を進めています。
【研究室紹介 https://www.kait.jp/research/navi/tkawaguchi.html】
●心地よいヒューマン-マシンインターフェイスの開発
振動システム実験室 教授 川島 豪
人の生活空間に機械が入るにつれ、危険を避けるために機械の不調などを素早く察知する必要があります。そこで本研究室では、振動や揺れの「ゆらぎ」に注目、どのような振動や揺れを用いれば心地よいヒューマン-マシンインターフェイスを構築できるのか明らかにしています。自然界の心地よいゆらぎに関しては、武者利光先生が「1/fゆらぎ」を提唱しています。しかし、「1/fゆらぎ」を人工的に創っても必ずしも心地よくありませんでした。そこで、その他の要因を究明するため、心地よく歩行している時の体の揺れを測定して周波数分析し、AIによりどのような特徴を用いて判別しているのか確認しています。この研究により多くの情報を心地よく伝達可能になることを期待しています。
【研究室紹介 https://www.kait.jp/research/navi/kawashima.html】
●高速道路でのV2V合流支援システムに必要な無線通信の条件抽出
コネクテッド・モビリティ研究室 教授 菊池典恭
私たちの研究室では、高速道路の合流をもっと安全でスムーズにする技術について研究しています。合流地点では、うまく本線に入れず渋滞が起きたり、事故のリスクが高まったりすることがあります。そこで近年では、車同士が無線通信で情報を共有し、お互いの位置や速度を確認しながら合流をサポートする合流支援システムが注目を集めています。この仕組みを実現するには、リアルタイムで安定した通信が欠かせません。無線通信は他の通信と電波を取り合うことがあるため、スムーズな合流にはどれくらいの通信性能が必要なのかを明らかにすることを目指す研究を進めております。
【研究室紹介 https://www.kait.jp/research/navi/kikuchi.html】
●熱機関の性能向上に関する研究
熱機関工学研究室 准教授 小池利康
産業現場で必要とされる環境・エネルギーに関する技術や課題を研究テーマとしています。例えば、「小型ガスタービンの性能計測計算,性能向上の研究」、「回り灯篭の熱力学的考察と実験」、「組立式防音ブースの製作と性能計測」、「実在気体の圧力・容積・温度(PVT)関係の研究」などを実施しています。近年、自動計測・制御化が進み、短時間に大量のデータを採取・計算することが可能となり、試験中に試験結果を確認して評価することも可能となってきています。測定の「不確かさ」も試験中瞬時に解析・評価し、不確かさの大きな測定項目を特定して「評価試験の信頼性を改善すること」も研究テーマに取り入れています。
【研究室紹介 https://www.kait.jp/research/navi/tkoike.html】
●ネットワーク情報共有型AIモビリティの研究
知能モビリティ研究室 助教 小宮聖司
AI自動運転や障害物回避等各種機能と作業目的を持ったモビリティがそれぞれ取得した情報をクラウド上で共有し相互活用することで統合された効率的なモビリティ運用を目指しています。
また、自動運転技術は、自動車事故低減、公共交通の充実、物流現場における人手不足解消、Maas等社会からの期待が大きく、さらなる技術向上と普及が重要となっている事から、車両製作、回路配線、運動制御、自動運転を総合的に実習・修得できるよう、自動運転学習支援教材の開発と実践を行っています。
【研究室紹介 https://www.kait.jp/research/navi/komiya.html】
●教育に活用する機械の検討
教育機械工学研究室 教授 佐藤智明
本研究室では、教育に活用する機械の開発および検討を主な研究テーマとしております。工学教育で活用する機械としては、教材用スターリングエンジンについて、その安全性や効果的な見せ方について検討しています。また、LEGOなどの玩具の教育活用も含め、構造を理解させるためのオリジナルのブロック教材の開発も行っています。更には、ロボットを用いた子供の情操教育、創造性教育、課題解決教育に貢献するロボットに関する検討を行っています。加えて、教育や啓蒙に活用する機械という意味においては、機械技術の遺産も教育機械の一種であると考え、機械技術の歴史的価値に関する調査研究および技術遺産のCG化についても検討しています。
【研究室紹介 https://www.kait.jp/research/navi/tsato.html】
●計測結果に基づいた実用的交通流物理モデルの開発と高速道路交通流での評価
流体物理工学研究室 教授 中根一朗
交通渋滞の発生は、CO2 の排出増加や国・地域の経済損失を伴います。交通流のシミュレーションは様々なモデルが提案されていますが、高速道路渋滞で見受けられるような自然渋滞への相転移とその解消を実用レベルで定量的に予測することはできていません。本研究では、交通流の計測結果から車両挙動の普遍性・相似性を見出し、自然渋滞への相転移とその解消(逆相転移)を予測できる物理モデルを提案するとともに、数値シミュレーションを利用して、天気予報のように、交通渋滞の発生・解消の予報をナビゲーションシステム等に発信するシステムの構築を目指しています。
【研究室紹介 https://www.kait.jp/research/navi/nakane.html】
●燃焼の数値シミュレーションによる燃焼排出物の評価
燃焼工学研究室 教授 林 直樹
二酸化炭素や窒素酸化物など燃焼器に由来する温暖化物質や大気汚染物質の低減は喫緊の課題です。本研究では、数値シミュレーションにより噴霧燃焼や水素燃焼など様々な燃焼場に対して、その排出物特性や火炎の特性の解明を目指しています。
【研究室紹介 https://www.kait.jp/research/navi/hayashi.html】
●ターボ圧縮機に発生する非定常流動の予知・制御に関する研究
熱流体工学研究室 准教授 萩野直人
ジェットエンジンやガスタービンで使用されているターボ圧縮機は出口を絞るとサージや旋回失速などの非定常流動が発生します。サージは圧縮機の軸方向、旋回失速は周方向の流れの自励振動であり、発生すると性能低下だけではなく圧縮機を含む管路系を破損させる恐れがあります。これらの非定常流動の発生前に圧力や流速に前兆が現れる場合があることが知られています。しかしながら、その発生過程はサージ・旋回失速の併発を含め不明な点が数多くあります。そこで本研究ではサージ・旋回失速の前兆現象を捉え、それらが大きく成長する前に検出し抑制制御を行う技術の開発を目指しています。
【研究室紹介 https://www.kait.jp/research/navi/hagino.html】
●超音波による工具接触圧力分布測定法に関する研究
生産システム研究室 助教 水野敏広
塑性加工では、被加工材・工具間の接触圧力を測定する方法として、従来側圧ピンや感圧紙等が用いられていますが、これらの方法は、測定のために何らかの形で接触面の状態及び性質を変化させますので、本来目的とする接触圧力を測定できないという欠点があります。そこで、本研究では、材料と工具の接触境界面に超音波が垂直入射すると、接触圧力の大きさに依存して超音波の反射特性が変化することに着目し、接触圧力と超音波の反射特性の相関関係から接触圧力を定量的に測定する方法の構築に取り組んでいます。
【研究室紹介 https://www.kait.jp/research/navi/mizuno.html】
●交通事故削減に資する車両運動制御技術の研究
車両運動・制御研究室 教授 山門 誠
私たちの研究室では,損害保険会社の自賠責運用益拠出事業の支援を受け,交通事故削減につながる車両制御技術の研究を行っています。現在は「G-Vectoring Control(GVC)」と車両安定化装置(ESC)を統合した制御を開発し、急な回避操作時でも車両が意のままに動く仕組みを検討しています。
さらに自動緊急ブレーキ(AEB)と連携させることで、単なるブレーキ作動にとどまらず、ハンドル操作を含めた総合的な衝突回避を可能にする点が特徴です。シミュレーションで有効性を確認しており、今後はクラウンスポーツPHEVを用いた実車試験での検証を予定しています。保険業界や自動車メーカーと協力しながら、「人の命を守る技術」の社会実装を進めていきます。
【関連URL https://jibai-info.jp/list/】
【研究室紹介 https://www.kait.jp/research/navi/yamakado.html】
●デザイン科学と破壊学に関する研究
構造デザイン研究室 教授 渡部武夫
切り紙構造の応用やフラードーム構造、CLT技術を用いた木質化構造など、様々な構造物、構造様式を対象に、デザイン科学的、構造・材料力学的アプローチで研究を実施しています。また、異分野の専門家とも連携し、機械的な破壊が創出する価値に着目した「破壊学」の研究を学際的に展開しています。
【研究室紹介 https://www.kait.jp/research/navi/twatanabe.html】
*****************************
メルマガのバックナンバーはこちら(https://cp.kanagawa-it.ac.jp/mailmagazine)へ
『研究・技術シーズ紹介』の内容や各種技術相談等、各種お問い合わせ
※お問い合わせカテゴリにて「共同研究・受託研究・研究機関に関すること」を選択してください。
https://www.kait.jp/contact/
【メールマガジン配信先変更・配信停止について】
https://cp.kanagawa-it.ac.jp/mailmagazine
******************************
==============================
メールマガジンの企画・編集・配信元
学校法人幾徳学園
神奈川工科大学 研究推進機構 研究広報部門
〒243-0292 神奈川県厚木市下荻野1030
e-mail:ken-koho@mlst.kanagawa-it.ac.jp
研究推進機構ウェブサイト
https://cp.kanagawa-it.ac.jp/
==============================
(C)2025 Kanagawa Institute of Technology. All Rights Reserved.