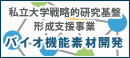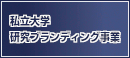産学官連携メールマガジン(2021年5月 特集:電気電子情報工学科)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【神奈川工科大学】産学官連携メールマガジン(2021年5月10日号)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールマガジンは、神奈川工科大学が主催するシンポジウムなどに参加された方、展示会などで名刺交換させていただいた方、関係機関の方々などに神奈川工科大学の研究・技術シーズ及び関連するニュースやイベント情報などを配信するメールサービスです。
配信先の変更・停止をご希望の方は、末尾をご参照ください。
『研究・技術シーズ紹介』へのお問い合わせは下記のURLからお願いいたします。
https://www.kait.jp/inquiry/inquiry.php?q=7
メールマガジンの読者登録/配信停止はこちらから
http://www.kanagawa-it.ac.jp/~l4024/mailmagazine/
メールマガジンバックナンバーはこちらから
http://ac-mail.jp/pub/bnk.php?pk=41f03fe79c92db43&mn=43098fc729075164
研究者研究シーズ検索はこちらから
http://www.kanagawa-it.ac.jp/~l4024/liaison/index.html
研究成果報告書等はこちらから
http://www.kanagawa-it.ac.jp/~l4024/research/index.html
技術相談など、各種お問合せはこちらから
https://www.kait.jp/inquiry/inquiry.php?q=7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
目次
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】研究・技術シーズ紹介(特集:工学部 電気電子情報工学科)
【2】ニュースリリース
【3】イベント情報(展示会・シンポジウム・フォーラム等)
【4】公募情報
(●:新規、◎:更新、○:再掲)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】研究・技術シーズ紹介(特集:電気電子情報工学科)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎太陽光発電システムの性能向上に関する研究
パワーエレクトロニクス研究室 教授 板子一隆
太陽光発電システムは環境に優しい新エネルギーとして注目され導入が進んでいます。当研究室では制御技術の観点からPVシステムの性能を向上させる研究を行っています。新型MPPT(最大電力点追従)制御技術によるエネルギー効率の改善、リアルタイムでのパネルのホット
スポットの検出法開発、パワーコンディショナのための新しいスイッチング技術(PCCS法)による電磁環境改善、PVを用いた災害時の非常用電源の開発などがあります。当研究室ではSDGsの開発目標、ターゲットに対応したこれらの技術開発により、新エネルギー社会の実現
を目指しています。
https://www.kait.jp/ug_gr/undergrad/engineering/electronics/academic/itako.html
http://www.ele.kanagawa-it.ac.jp/~itako/index.html
〇低損失半導体ダイオードの研究
電子デバイス研究室 教授 工藤嗣友
本研究では、次の要求事項を満足する低損失半導体素子の開発を行っている。(1)LSIの動作電圧が低減化にともない、これを駆動するスイッチング電源回路用ダイオードの開発。(2)再生可能エネルギーである太陽電池用低損失バイパスダイオードの開発を中心に行っている。従
来の低オン電圧として使用されるショットキーバリアダイオードは、温度上昇にともない逆方向リーク電流が増加し事故加熱による熱暴走が生じ破壊を生じます。開発中のダイオードは、高温時(約175℃)でも熱暴走せず整流特性を得ている。本提案デバイス構造はユニポーラ構造とバイポーラ構造の合わさったデバイス構造なのでスイッチング損失が小さい特性が得られています。
https://www.kait.jp/ug_gr/undergrad/engineering/electronics/academic/kudo.html
http://www.ele.kanagawa-it.ac.jp/~kudoh/
〇電子測定器の高精度化のために
先端電子計測研究室 教授 小室貴紀
電気的な現象は人間の五感では捉えられませんので、電子機器の動作を確認するには測定器が必要です。また、その測定器が正しい値を出すことを保証するためには、定期的に校正作業を行う必要がありますが、安価で間違いなく遂行するために、A-Cardによる新しい方法を提案し、特許提案と学会発表を行いました。現在事業化に向けて準備を進めています。さらに測定機器を安定に動作させるために、環境温度の変化を打消す恒温槽の研究も行っています。研究では実験に加えてシミュレーションも行いますが、電子回路向けと熱現象向けのシミュレータは動作原理が異なるため、協調させることが困難です。この問題に対応したシミュレーションの方法も検討しています。
https://www.kait.jp/ug_gr/undergrad/engineering/electronics/academic/komuro.html
http://www.ele.kanagawa-it.ac.jp/~komuro/
〇放電・プラズマを利用した空気浄化の研究
電気応用研究室 教授 瑞慶覧章朝
電気集塵技術を基軸に、放電・プラズマを利用した排ガスや室内空気中の浮遊粒子状物質、有害ガスや細菌の除去に関する研究を進めている。コロナ放電,バリア放電,パルスストリーマ放電などの非熱平衡大気圧プラズマや高電界を利用し、排ガス中のブラックカーボン、硫酸塩、可溶性有機成分(SOF)、多環芳香族炭化水素(PAHs)、SOx、NOxなどを除去している。
また、室内空気の殺菌を目的として、黄色ブドウ球菌の殺菌効果に対するコロナ放電、電界やイオンの影響を蛍光顕微鏡や電子顕微鏡など様々な手法を用いて多角的に検討している。コロナ放電によって発生する電気流体のシミュレーション及びPIVを用いた計測も行っている。室内空気
環境、船舶排ガスや火力発電所等の排ガス浄化など、大切な空気環境を守るために研究を推進している。
https://www.kait.jp/ug_gr/undergrad/engineering/electronics/academic/zukeran.html
http://www.ele.kanagawa-it.ac.jp/~zukeran/
○車載センサ情報共有型車両情報共有システム
モビリティITC研究室 准教授 高取祐介
自車両の走行情報と、車載障害物検出用センサで取得した周辺他車両の走行情報を、車車間通信で共有するシステムの研究を行っている。車載障害物検出用センサが苦手とする見通し外の車両情報に関して、自車の情報のみを送信する車車間通信では取得できないシステム車載器非搭載車情報を取得できる点が本システムの強みである。これは実際のシステム普及段階における運用環境(車載器搭載車両・非搭載車両混在環境)においてその強みが発揮されることが期待されている。本研究では、交通量やシステム車載器普及率がシステムの周辺車両情報取得性能に及ぼす影響についてミクロスコピック交通流シミュレータを構築し解析を行っている。
https://www.kait.jp/ug_gr/undergrad/engineering/electronics/academic/takatori.html
〇有彩色照明光が生体に及ぼす効果の解明
視環境研究室 准教授 高橋 宏
近年、LED照明の普及に伴い、照明の光色が注目されている。実際に光色制御可能なLEDシーリングライトやLED電球も市販されており、照明の光色は今後ますます注目されると考えられる。しかし、有彩色光が生体に及ぼす効果は明らかにされておらず、現状では有効な利用法が見出せていない。そこで本研究では、有彩色光の効果的な利用法の提案を目指して、照明の光色が生体に及ぼす視覚的および非視覚的効果を、主観評価や生理評価を行うことで明らかにする。現在は脳波測定による覚醒度の変化に注目した研究を進めており、光色による覚醒度への影響が確認されている。また、光色環境が味覚閾値に及ぼす影響についても研究を進めており、より実用的な光色利用法の提案を目指している。
https://www.kait.jp/ug_gr/undergrad/engineering/electronics/academic/takahashi.html
○AIによる次世代に向けた画像情報システムの探求
AI・画像工学研究室 教授 武尾英哉
電子工学技術の進展に伴い、デジカメや携帯電話のカメラ機能など、多くのディジタル画像が普及してきました。本研究では、これらディジタル画像をコンピュータを使って美しくする表現方法、すなわちディジタル画像処理技術について研究を進めています。また、すでに多くの病院でも画像のディジタル化は進んでおり、医用画像工学という分野が確立されています。この分野で臨床応用されている画像認識システムについても研究しています。画像診断支援技術(CAD:Computer Aided Diagnosis)と呼ばれ、機械学習やAIを用いて画像から自動的に病変候補を検出し、それを医師に提示することで診断能の向上を図る狙いです。特徴量を用いた統計的手法による判別方法(機械学習)を主としていますが、最新のディープラーニング(深層学習)による判別方法も検討しています。
https://www.kait.jp/ug_gr/undergrad/engineering/electronics/academic/takeo.html
http://www.ele.kanagawa-it.ac.jp/~takeo/
◎集積形光機能デバイスの研究
光機能デバイス研究室 教授 中津原克己
ビデオ会議や様々な動画の視聴など、無線基地局やWi―Fiルータの先に繋がる光通信ネットワークのデータ伝送能力によって支えられています。今後もさらに増大が予想されるデータ量に対応するためにネットワークの機能向上ならびに低消費電力化が望まれています。
当研究室では、電子ビーム描画装置やスパッタリング装置など本学の研究設備を駆使し、企業や他の研究機関(東工大、沼津高専、香川大)と連携しながら、導波路形光スイッチや光サーキュレータなど集積化に適した通信用光デバイスの研究開発を行っています。また、極微小領域に高いパワー密度の光を局在させる水平スロット導波路を用いたセンサデバイスの研究開発も進めています。
https://www.kait.jp/ug_gr/undergrad/engineering/electronics/academic/nakatsuhara.html
http://www.ele.kanagawa-it.ac.jp/~naka2/01_home/index.html
〇電子回路上の非線形波動制御に基づく信号生成制御技術
非線形波動工学研究室 教授 楢原浩一
本研究では、電界効果トランジスタや量子効果素子を分布定数的に用いるプラットフォーム上に誘起される様々な非線形波動現象を電気信号生成制御技術に応用することを目的としています。ムーアの法則に従って半導体素子・回路の集積率は増大を続けています。ここに来てその限界が議論されるに至っています。集積率向上の一つの目的は信号処理の高速化にあります。速度性能向上に特化する場合、ムーアの法則から外れた新しい処理形態が求められています。非線形波動制御は将来の高速処理に適した手法を提供します。例えば散逸ソリトン間に生ずる斥力を有効利用してタイミング・ジッタを軽減するなど従来にない手法を提案しています。
https://www.kait.jp/ug_gr/undergrad/engineering/electronics/academic/narahara.html
http://www.ele.kanagawa-it.ac.jp/~narahara
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】ニュースリリース
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2021.04.13
ホームエレクトロニクス開発学科4年生が情報処理学会全国大会で学生奨励賞を受賞
https://www.kait.jp/news/1804.html
2021.04.14
DIVPプロジェクトがYouTubeで公開されました
https://www.kait.jp/news/1805.html
2021.04.16
ロボット・メカトロニクス学科4年生が、情報処理学会全国大会で学生奨励賞を受賞
https://www.kait.jp/news/1806.html
2021.04.16
AIで本学のソーラーパネルの発電量を予測
(機械工学科/先進太陽エネルギー利用研究所教授川島 豪 )
https://www.kait.jp/tech_news/90.html
https://www.kait.jp/ug_gr/undergrad/engineering/mechanical/academic/kawashima.html
http://www.me.kanagawa-it.ac.jp/kawashima/
2021.04.30
スマートウォッチを用いたジェスチャー認証
(セキュリティー研究センター/情報ネットワーク・コミュニケーション学科教授岡崎美蘭)
https://www.kait.jp/tech_news/91.html
https://www.kait.jp/ug_gr/undergrad/info_science/infoNW_com/academic/okazaki.html