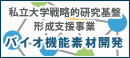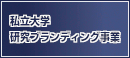産学官連携メールマガジン(2021年7月9日 臨床工学科特集号)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【神奈川工科大学】産学官連携メールマガジン(2021年7月9日号)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールマガジンは、神奈川工科大学が主催するシンポジウムなどに参加された方、
展示会などで名刺交換させていただいた方、関係機関の方々などに神奈川工科大学の研究・
技術シーズ及び関連するニュースやイベント情報などを配信するメールサービスです。
配信先の変更・停止をご希望の方は、末尾をご参照ください。
『研究・技術シーズ紹介』へのお問い合わせは下記のURLからお願いいたします。
https://www.kait.jp/inquiry/inquiry.php?q=7
メールマガジンの読者登録/配信停止はこちらから
http://www.kanagawa-it.ac.jp/~l4024/mailmagazine/
メールマガジンバックナンバーはこちらから
http://ac-mail.jp/pub/bnk.php?pk=41f03fe79c92db43&mn=43098fc729075164
研究者研究シーズ検索はこちらから
http://www.kanagawa-it.ac.jp/~l4024/liaison/index.html
研究成果報告書等はこちらから
http://www.kanagawa-it.ac.jp/~l4024/research/index.html
技術相談など、各種お問合せはこちらから
https://www.kait.jp/inquiry/inquiry.php?q=7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
目次
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】研究・技術シーズ紹介(特集:健康医療科学部 臨床工学科)
【2】ニュースリリース
【3】イベント情報(展示会・シンポジウム・フォーラム等)
【4】公募情報
(●:新規、◎:更新、○:再掲)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】研究・技術シーズ紹介(特集:臨床工学科)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○腱反射の計測と定量化
人間センシング研究室 准教授 大瀧保明
腱反射は脚気の検査としても一般に知られ、ハンマーひとつで行える神経疾患の基本的な検査
方法である。臨床医は目的とする筋の腱をハンマーで叩打して反射を誘発する。障害部位によっ
て反射の程度に差を生ずるが、反射応答に対する診断は臨床医の視認に依っている。我々は臨床
手技としての叩打検査の利便性は阻害しない形で、叩打刺激に対する反射応答を定量評価する携
帯型機器の開発を行っている。力センサと慣性センサの計測データから、下肢に物理モデルを仮
定して入出力関係のシステム同定を行い、反射応答の特徴抽出と鑑別への利用を提案している。
今後、健常例と神経疾患症例における本法の妥当性について検証を重ねる必要がある。
https://www.kait.jp/ug_gr/undergrad/engineering/clinical/academic/ootaki.html
◎情報処理システムでの高度なエネルギー供給を目指して
情報システム電力変換工学研究室 教授 河口進一
サーバ計算機、情報端末、医療機器の中の情報処理ではCPU、GPU等、各種プロセッシン
グユニットが中心的な役割を担っています。これらが計算処理を行うためには多くの電力を必要
とします。一般的にプロセッシングユニットでの電力負荷は低電圧、大電流かつ急激な負荷変動
を伴う厳しい特性を持つと言われています。プロセッシングユニットに対して安定かつ高効率な
電力供給を行うためには、情報処理システムが実際の計算処理を行う際に、どのように電力を
消費するのかを明らかにする必要があります。さらにそれらの知見を活かし、プロセッシングユ
ニットでの電力消費を短時間かつ正確に予測して、最適な電力供給制御を可能とする新たな高効
率電源システム方式が求められます。このように、情報処理状態に応じた電力推定によるアダプ
ティブ制御を実現することにより、情報処理システムでの高度なエネルギー供給を目指します。
https://www.kait.jp/ug_gr/undergrad/health/clinical/academic/kawaguchi.html
●医療情報を利用したAI(深層学習)による予測モデル構築に関する研究
臨床工学医療情報研究室 助教 川崎路浩
患者自身の医療情報や治療によって蓄積される医療情報は、デジタル化社会において膨大な量
となってきている(ビッグデータ)。そのデータを医療機関の協力を得てAI、特に深層学習と
いう技術を利用して、例えば血液透析治療における血圧低下予測や人工心肺中のヘモグロビン値
の予測などをおこなう、「予測モデル」の構築に挑んでいる。現在は、2種類のモデルが完成し
て、それぞれのモデルの精度確認やパラメータ調整をおこなっている。このモデルを医療現場で
利用することができれば、治療の質の向上や医療従事者の負担軽減に寄与できる取り組みである。
https://www.kait.jp/ug_gr/undergrad/health/clinical/academic/kawasaki.html
○医療機器における医療従事者の操作や不具合探索における認知研究
クリニカルイノベーションマネジメント(CIM)研究室 教授 鈴木 聡
医療機器インターフェースの完成度は高くなく、その要因のひとつは使われ方に対する検討
(ユーザの知識や技能だけでなく、操作環境や心理など)が十分でないことが挙げられる。同じ
目的の機器でもインターフェース設計によって使いやすさや操作エラーには大きな影響を与える。
本研究室では、様々な職種や知識レベルの異なる医療従事者などが、一定の条件および環境の中
で遂行するタスク方略(どのように状況を認識し、行動の計画をたてて作業を遂行するか)に関
する研究を行っている。また医療上の作業に対する技能評価や、習熟に関する検討、さらに臨床
の組織文化に関する検討を行っている。これらは視線解析や動作分析・タスク分析や、調査票な
どといった人間工学の方法を利用し、医療従事者の教育や医療機器インターフェースの適正化を
目指した研究を行っている。
https://www.kait.jp/ug_gr/undergrad/health/clinical/academic/suzuki.html
◎体位変換が循環動態に及ぼす影響とその調節に関する研究
生体情報研究室 助教 西村宗修
ヒトは重力の存在下で生活しており、無意識のうちに様々な影響を受けている。例えば、水平
仰臥位から立位へと瞬時に体位変換すると、静水圧勾配によって下肢方向に約500mlの体液が
シフトする。この時に、圧受容器反射をはじめとした神経性調節機構が適切に働かないと、脳へ
の供血量が不足して立ち眩みや失神を起こす。このように、姿勢の変化が生体に及ぼす影響は小
さくなく、恒常性を維持するための調節機構の働きは、生活の質にも大きく関わる。我々は、
様々な姿勢とその変化が循環動態に及ぼす影響、特に血圧調節に関するデータの蓄積と分析を
行っている。循環系デコンディショニングに対して臨床的な対策を講ずる際に、必要となる基礎
データを供する事を目的に研究を進めている。
https://www.kait.jp/ug_gr/undergrad/health/clinical/academic/nishimura.html
○難治性疾患の克服を目指したリンパ管・リンパ組織の可塑性の研究と新規治療法の開発
臨床工学科 特任教授 馬嶋正隆
本研究では、リンパ組織の可塑性の変調・不全を基盤として発症する難治性疾患を標的に、治
療ツールとしての生理活性脂質の有効性を検討する。具体的には(1)可塑性の基盤となるリン
パ管内皮細胞の動態を制御する生理活性脂質を同定し、(2)個体レベルでもリンパ組織の可塑
性を制御するか検討する。さらに、得られた成果を基に(3)リンパ浮腫、(4)がんのリン
パ行性転移というリンパ組織の可塑性の変調・不全を基盤として発症する難治性疾患の新規治療
法開発を試みる。また、(5)生体イメージング手法を用いてリンパ管による脂質循環の破綻が
引き起こす代謝疾患の新規治療法を検討する。リンパ組織は、炎症をはじめとする疾患の発症、
組織再生の場として重要である。リンパ管の存在は100年以上前から明らかにされていたにも
かかわらず、本格的に研究が進みはじめたのはここ10年ほどであり、現在も国内外で次々に新
しい発見が続くホットな研究領域である。これまで注目されてこなかったリンパ管機能に焦点を
あて、関連する疾患発症に関わるメカニズムを解析、治療的介入を進めて来た例は極めて少ない。
斬新な研究であり、研究成果が上がれば、その波及効果が大いに期待できる研究取り組みである。
https://www.kait.jp/ug_gr/undergrad/health/clinical/academic/majima.html
https://department-of-medical-therapeutics6.webnode.jp/
◎脳血液循環に関する分野融合的研究
生体計測研究室 特任教授 松尾 崇
活動時の脳血液循環の特性を明らかにすること、およびその結果を実際の問題の解決(脳血管
病変の発生要因解明および体への負担の小さい介護動作)に活用することを目的に、次の研究を
行っている。(1)「運動・作業における中大脳動脈血流波形と指先血圧の同時測定」。(2)
「脳血管構築の流体力学的特徴と脳血管病変との関連」。前者は超音波ドップラ流速計により、
能動的動作時の脳血流波形の測定を行っている。血流波形の力学的解析により、血管壁にかかる
血流負荷(最低・最高・平均血流速、流速の変動度、抵抗指数など)を算出する。また、脳では
血液循環に関連する疾患(脳出血、くも膜下出血や循環障害性の脳病変など)が好発し、それぞ
れの病変はある決まった部位に発生しやすいという部位特異性が知られている。この部位特異性
を明らかにするために、脳血管の幾何学的形態の特徴について、流体力学を基礎に解析している。
https://www.kait.jp/ug_gr/undergrad/health/clinical/academic/matsuo.html
●皮膚接触を利用したコミュニケーションに関する研究
ライフサポート工学研究室 教授 松田康広
コロナ禍で私たちは、人と人の皮膚接触を控える生活を続けています。皮膚接触は、相手との
親密さや愛情を表す重要なコミュニケーション手段です。しかし、親しくない相手との間には社
会的距離があり、親しくない相手がその距離内に入ると不安を感じます。そこで社会的距離を保
ちながら、皮膚接触によるコミュニケーションを行えるような、コミュニケーション補助ツール
を開発しています。補助ツールは、ソフトテニスボール2個に穴を開け、ゴム製チューブを接続
したもので、一方のボールを握ると、もう一方のボールが膨らむというものです。これまで、
音声会話中に補助ツールがどのように使われるか、補助ツールによってどのように感情を表現し、
どの程度伝達できるのか、研究を進めています。
https://www.kait.jp/ug_gr/undergrad/health/clinical/academic/matsuda.html
〇血液浄化療法における操作技術の標準化に関する研究
血液浄化技術研究室 特任教授 山家敏彦
血液浄化療法は、血液中に存在する病因関連物質を除去することで病態の改善を図る体外循環
療法である。内科、外科領域を問わず急性・慢性疾患、救命救急治療、難病など極めて広い領域
で適応される。なかでも膜型血液濾過器を用いたアフェレシス療法は、日本発の治療方法として
開発されたものの世界への普及は十分ではない。現在、血液濾過器のみならず吸着剤を用い血液
中の病因関連物質を量的、質的に調整する方法も普及し、多くの疾患で治療効果が得られている。
血液濾過器や吸着剤の操作手技は未だに標準化されていないことが多く、世界への普及を遅らせ
ている原因の一つとなっている。操作手技の標準化を実現することは、治療装置の安全操作と直
結するものであり、体外循環治療の安全確保に大きく寄与するものである。現在、当研究室では、
難治性胸・腹水濾過濃縮法、血液回路内表面構造の違いによる抗血栓性への影響、災害時におけ
る血液浄化療法への安全対策などの研究を進めている。
https://www.kait.jp/ug_gr/undergrad/health/clinical/academic/yanbe.html
○ドーピング防止教育の意義に関する調査研究
運動生理・健康科学研究室 教授 渡邉紳一
これまで、主として柔道競技において、アンチ・ドーピングに関する意識調査を国内トップレ
ベルの中高生選手、日本代表選手とドーピング競技会検査の帯同者、中学全国大会出場選手とそ
の競技者支援要員を対象として実施し、7編の論文で報告してきた。これらの報告では、ドーピ
ング防止教育の早期導入の重要性、検査対象となることは一流選手の証であり自身がクリーンで
あることを証明する機会であることを理解させる反復教育の重要性、競技者支援要員のアンチ・
ドーピングに対する積極的理解の重要性などを示してきた。現在は、2021年の東京五輪など
で違反者を出さないようにするための基礎的知見を得るために意識調査を実施しており、ドーピ
ング防止教育の意義についての再検討を行なっている。
https://www.kait.jp/ug_gr/undergrad/health/clinical/academic/watanabe.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】ニュースリリース
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2021.06.16
eスポーツを産学連携で盛り上げる神奈川工科大学とNTT東日本の取り組み
https://news.mynavi.jp/article/20210616-1901019/
2021.06.11
先進eスポーツ研究センターの取り組み
(情報ネットワーク・コミュニケーション学科/先進eスポーツ研究センター 教授 塩川茂樹)
https://www.kait.jp/tech_news/94.html
2021.06.25
eスポーツにおける音・音楽の役割!?
(情報メディア学科/先進eスポーツ研究センター 准教授 上田麻理)
https://www.kait.jp/tech_news/95.html
*******************************************
技術相談、各種お問合せ
https://www.kait.jp/inquiry/inquiry.php?q=7
メールマガジンの読者登録/配信停止
http://www.kanagawa-it.ac.jp/~l4024/mailmagazine/
メールマガジンバックナンバー
http://ac-mail.jp/pub/bnk.php?pk=41f03fe79c92db43&mn=43098fc729075164
*******************************************
===========================================
メールマガジンの企画・編集・配信元
学校法人幾徳学園 神奈川工科大学 工学教育研究推進機構 リエゾンオフィス
電話:046-291-3277 又は046-291-3304
e-mail:liaison@kait.jp
Copyright(C)2017-2021 KAIT All Rights Reserved.
===========================================