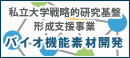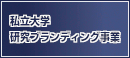【KAIT産学官連携メルマガ】応用化学生物学科特集(その1)(2025年2月14日号)
※本メールマガジンは、神奈川工科大学(KAIT)が主催するシンポジウム等に参加された方、展示会等で名刺交換させていただいた方、関係機関の方々に配信しております。
※配信先の変更・停止をご希望の方は、末尾をご参照ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
目次
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】新着ニュース
【2】YouTube「神奈川工科大学 研究推進機構チャンネル」
【3】研究・技術シーズ紹介(応用化学生物学科)
●腫瘍細胞にアポトーシスを誘導する成分の発見
●膜ろ過法を利用したナノマテリアルの分離精製技術の開発
●線虫C. elegansおよび哺乳動物培養細胞を用いた健康寿命延長に寄与する生理活性物質の探索と同定および機能解析
●組織培養による薬用植物の大量増殖技術の開発
●ケミカルループを利用した廃棄物処理システムの開発
●タンパク質から見た食品の研究
●酵素の反応機構を利用したタンパク質性カプセルの開発
●深海に生息する水素エネルギーを生み出す微生物の探索
●イソソルビドからの新規重縮合、重付加モノマーの合成と高性能バイオベースエンジニアリングポリマー及び耐熱性熱硬化性樹脂合成への展開
●セラミックスの低温焼結化と電子デバイス等への応用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】新着ニュース
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
先進eスポーツ研究センターの取り組み(先進eスポーツ研究センター/情報ネットワーク・コミュニケーション学科 教授 塩川茂樹)
https://www.kait.jp/tech_news/ee.html
【記事を掲載していただきました】画像処理AI技術を用いて動画から特定の音だけを除去 (※つくばサイエンスニュース様のサイトが開きます)
https://x.gd/hrYP2
神奈川工科大学 スマートハウス研究センター、国際標準化会議でECHONET Lite AIFのデモンストレーションを実施
https://cp.kanagawa-it.ac.jp/press/2807.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】YouTube「神奈川工科大学 研究推進機構チャンネル」
https://www.youtube.com/@KikouKAIT
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今号の動画は、
『【オープンラボ紹介動画】バーチャルリアリティーを利用したタンパク質の見える化と直感的創薬デザイン』
※第一回リサーチデーでのオープンラボ紹介動画です。
https://youtu.be/kc7WJ4ztuak?feature=shared
機構のX(旧Twitter)はこちらへ
https://x.com/KikouKAIT
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】研究・技術シーズ紹介
《特集》応用化学生物学科
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●腫瘍細胞にアポトーシスを誘導する成分の発見
生物制御科学研究室 教授 飯田泰広
多くのがん細胞では、アポトーシス機能が抑制されており、無制限な増殖や抗がん剤への耐性の要因になることが知られています。私達は、様々ながん細胞で高発現しているSurvivinとHBXIPが複合体を形成してアポトーシスを抑制していることに着目し、複合体の形成を容易に評価するシステムを開発しました。その結合活性を指標にして生薬抽出物を対象にSurvivin-HBXIP複合体形成阻害物質を探索しました。また、複合体形成阻害能を有する抽出物をがん細胞(悪性黒色腫、肺がん、膵がんの細胞)に作用させることでそれらのがん細胞にアポトーシスを誘導することを見出しました。これらの成分の中に、新たな抗腫瘍活性物質が含まれていると期待しています。
https://www.kait.jp/research/navi/iida.html
http://iida.biokait.jp/iida/welcome.html
●膜ろ過法を利用したナノマテリアルの分離精製技術の開発
膜分離工学研究室 教授 市村重俊
均一なナノサイズの物質を高濃度で効率良く回収する分離精製操作は一般に煩雑なものとなります。膜ろ過法は、これを容易に連続的に行えるため期待されていますが、物質の吸着や堆積により性能が低下するファウリング現象への対策が不可欠です。そこで当研究室では、ナノマテリアルと膜との相互作用を膜の表面修飾により制御することで、高い耐ファウリング性を持つろ過膜を開発しています。また、膜の性能を最大限発揮するためには堆積抑制技術も必要となるため、分散凝集挙動も含めた現象の解明、ろ過条件の最適化手法についてもあわせて検討しています。
https://www.kait.jp/research/navi/ichimura.html
http://ichi.biokait.jp/ichi/Welcome.html
●線虫C. elegansおよび哺乳動物培養細胞を用いた健康寿命延長に寄与する生理活性物質の探索と同定および機能解析
老化・疾患生物学研究室 教授 井上英樹
植物や食材に含まれる生物由来の生理活性物質が生物の健康状態の向上に寄与することが知られています。当研究室では遺伝子および細胞内機構がヒトと共通している線虫C. elegans(ガンを匂いで探索すると話題になった生物です)および、哺乳動物培養細胞を用いて健康に寄与する生理活性物質を探索、単離・同定し、その作用機序の解明を進めています。最近は特に、皮膚の老化を抑えたり傷の修復を促進したりする作用を持つ生理活性物質や、がんの転移や悪性化を抑えることが期待される生理活性物質の作用機序の解明に焦点を合わせ研究を進めており、健康長寿を実現するための基礎となる知見確立を目指しています。
https://www.kait.jp/research/navi/hinoue.html
http://inoue.biokait.jp/index.html
●組織培養による薬用植物の大量増殖技術の開発
植物細胞工学研究室 教授 岩本 嗣
漢方薬に対する関心の高まりとともに、漢方薬の市場規模は拡大傾向にありますが、日本での生産量は少なく、海外からの輸入に依存しているため、安定供給に対する懸念が大きいです。また、類似品や有効成分含量が少ない粗悪品の混入が問題となっているため、成分含量の揃った漢方薬の安定供給が急務となっています。そこで、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の依頼を受け、漢方薬の材料となる薬用植物の無菌培養系の確立と組織培養による大量増殖技術の開発に取り組んでいます。
https://www.kait.jp/research/navi/iwamoto.html
●ケミカルループを利用した廃棄物処理システムの開発
資源エネルギーシステム研究室 准教授 大庭武泰
ケミカルループ燃焼法(chemical looping combustion)は、化石燃料の燃焼反応を2つの反応(金属酸化物中の酸素と燃料の反応、還元された金属と空気中の酸素との反応)に分けて行う方法です。この方法では二酸化炭素が分離された状態で排出されます。現在、この方法を廃棄物の処理に応用するための実証研究を実施中で、実現すると廃棄物から二酸化炭素とエネルギーの両方が得られることになります。
https://www.kait.jp/research/navi/ohba.html
●タンパク質から見た食品の研究
水産化学研究室 准教授 小澤秀夫
食物アレルゲンの原因物質は、食品中に含まれるタンパク質です。特定原材料に指定されているエビのアレルゲン除去法を開発しました。分子動力学シミュレーションは、蛋白質構造データバンクに登録されているタンパク質およびそれらの近縁タンパク質を対象にタンパク質のふるまいを計算機により再現する手法です。
現在は、魚肉の赤色を担うミオグロビンを対象とし、その変色機構の分子機構を検討しています。
https://www.kait.jp/research/navi/ozawa.html
http://ozawa.biokait.jp/
●酵素の反応機構を利用したタンパク質性カプセルの開発
分子機能科学研究室 教授 小池あゆみ
生物がもつシャペロニンというタンパク質を、ナノサイズのカプセルとして医療分野や工学分野に応用する研究をしています。私たちは、直径2~5nmの人工的な金属粒子を95%の効率でシャペロニンの2つの空洞に順番に閉じ込めることに成功しました。凝集性の高い金属ナノ粒子や化合物が水溶液中で安定に分散し、また、数nmの近い距離に配置することが可能となりました。金属ナノ粒子はがん治療や人工光合成などへの応用が可能であることから、医療や持続可能なエネルギー源の開発が期待できます。また、この技術は金属ナノ粒子だけでなく薬物(化合物)の内包にも適用できることから、ドラッグデリバリーシステムにも応用できます。
https://www.kait.jp/research/navi/koike.html
http://koike.biokait.jp/koike/Welcome.html
●深海に生息する水素エネルギーを生み出す微生物の探索
環境化学・環境生物研究室 教授 齋藤 貴
極限環境である深海に生息している生物はいまだ未知の世界です。齋藤研究室では、調査研究用潜水艇により採取した深海の海底堆積物を培養して遺伝子解析を行い、クリーンエネルギーとしての水素を発生する微生物の探索を行っています。これまで、マリアナ海溝(水深数千m)の断層帯周辺について探索を行ったところ、水素ガスを代謝する複数の微生物を発見しました。圧力が非常に高い深海でも生きていて活動しているとは驚きです。アルコールを生産する微生物も同時に発見しました。現在、伊豆半島沖の水深数百mの海底火山があった海底について、地層中の微生物を分析中です。新種の微生物を見つけようと研究生は日々研究に取り組んでいます。
https://www.kait.jp/research/navi/saito.html
●イソソルビドからの新規重縮合、重付加モノマーの合成と高性能バイオベースエンジニアリングポリマー及び耐熱性熱硬化性樹脂合成への展開
高分子化学研究室 教授 三枝康男
脱石油依存を目指して、バイオベースポリマーの合成が急速な展開を見せています。デンプンより誘導されるイソソルビドは医薬品(利尿剤)として利用されていますが、これを共重合したポリカーボネートが軽量かつ破損し難いガラス代替品(フロントパネル)として一部のスマートフォンで採用されています。これまでに、イソソルビドより新しい重縮合モノマーとなる酸無水物へ誘導して、これより十分な耐熱性とフィルム強度、溶媒可溶性を持つ一方で、溶融可能でUV-Vis透過性のよい一連のポリイミドを合成したことについて報告してきました。その後の進展として、ビスマレイミドに例示される重付加モノマーを新たに合成して、ジアミンとの重付加反応によるポリアミノイミドの合成、さらにはこのオリゴマーを熱硬化させた耐熱性熱硬化性樹脂の合成へと展開を図っています。実用的見地からも両バイオベースポリマーの物性には興味が持たれるところです。
https://www.kait.jp/research/navi/ysaegusa.html
●セラミックスの低温焼結化と電子デバイス等への応用
ファインセラミックス研究室 教授 茂野交市
陶磁器などに代表されるセラミックスを製造するには通常約1300℃以上の高温で焼結(焼成)する必要があります。これをより低温で焼結できれば省エネルギー化に直接貢献することができます。私たちは1000℃未満でセラミックスを焼結する技術を開発し、さらにこの技術をスマートフォンなど電子デバイスの小型化などに応用することを目指しています。
https://www.kait.jp/research/navi/shigeno.html
******************************
メルマガのバックナンバーはこちらへ
メールマガジン – 神奈川工科大学 研究推進機構 (kanagawa-it.ac.jp)
『研究・技術シーズ紹介』の内容や各種技術相談等、各種お問い合わせ
※お問い合わせカテゴリにて「共同研究・受託研究・研究機関に関すること」を選択してください。
https://www.kait.jp/contact/
【メールマガジン配信先変更・配信停止について】
https://cp.kanagawa-it.ac.jp/mailmagazine
******************************
==============================
メールマガジンの企画・編集・配信元
学校法人幾徳学園
神奈川工科大学 研究推進機構 研究広報部門
〒243-0292 神奈川県厚木市下荻野1030
e-mail:ken-koho@mlst.kanagawa-it.ac.jp
研究推進機構ウェブサイト
https://cp.kanagawa-it.ac.jp/
==============================
(C)2025 Kanagawa Institute of Technology. All Rights Reserved.